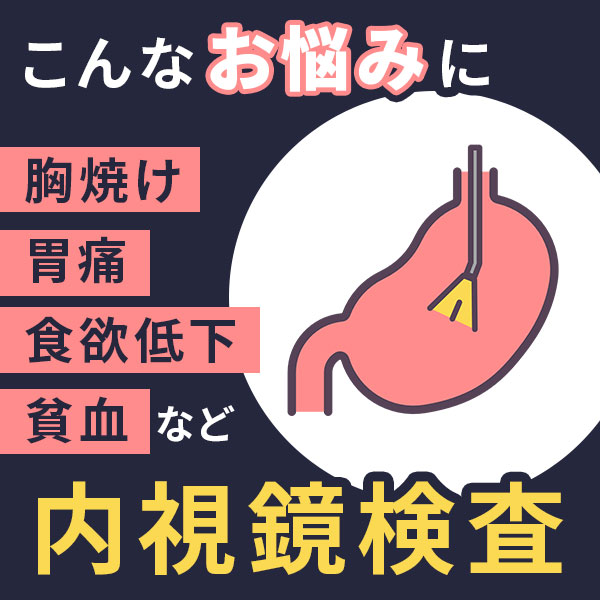脂質の摂取適正量
脂質の理想的な摂取量は、総エネルギーの20~25%。成人では、1日およそ40~60g程度が目安です。 これは、炒め油などの調理に使う「見える油脂」と、食品そのものに含まれている「見えない油脂」を合わせた量の目安となります。1日の脂質摂取量のうち、「見える油」が20%であり、残りの80%は「見えない油脂」と言われています。そのため、1日の「見える油脂」の使用量は大さじ1~2程度にする必要があります。
脂質を多く含む食品と脂質量
- 豚バラ肉100g 脂質:約35g
- ウインナー3本(約60g) 脂質:約18g
- からあげ4個(約100g) 脂質:約23g
- アイス(スーパーカップ)1個 脂質:約23g
- 板チョコ1枚(50g) 脂質:約17g
脂質の1日の適正量が40~60gとすると、1食は15~20g程度となります。
豚バラ肉は脂をたっぷり含んでいるため、約100g食べただけで簡単に2食分程度の脂質を摂ってしまいます。また、間食でお菓子を食べる場合はより注意が必要です。軽い間食のつもりでも、揚げ物を食べたときと同じくらいの脂質を摂っていることになります。
加工食品には「栄養成分表示」が必ず記載されているため、購入する際には脂質の低いものを選ぶなど、事前に確認をしてから食べる量を調整しましょう。
脂の種類
油脂は大きく分けて「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」に分かれます。
飽和脂肪酸
常温で個体に変化します。肥満や生活習慣病のリスクが高まるため、摂りすぎないよう注意が必要です。
作用:HDLコレステロール(善玉)を減少させ、LDLコレステロール(悪玉)を増加させる。
多く含まれる食品:肉や乳製品(バターや生クリームなど)
不飽和脂肪酸
常温で液体に変化します。高温で調理すると過酸化脂質になるため、ドレッシングなどで摂るのがおすすめです。
作用:LDLコレステロール(悪玉)を減少させる。
多く含まれる食品:植物油や魚類(マグロ・サンマ・サバなど)
不飽和脂肪酸はさらに、構造の違いによって「一価不飽和脂肪酸」と「多価不飽和脂肪酸」に分けられます。
一価不飽和脂肪酸
- n-9系脂肪酸(ほどほどに摂りたい油脂)
作用:LDLコレステロール(悪玉)を減少させる
多く含まれる食品:オリーブ油、米油
多価不飽和脂肪酸
- n‐3系脂肪酸(意識して摂りたい油脂)
作用:中性脂肪を減少させる、血管の保護作用、血液をサラサラにする
多く含まれる食品:青魚、アマニ油、えごま油、しそ油 - n‐6系脂肪酸(できるだけ控えたい油脂)
作用:HDLコレステロール(善玉)を減少させる
多く含まれる食品:サラダ油、大豆油、ごま油
トランス脂肪酸(できるだけ控えたい油脂)
トランス脂肪酸は、脂質の構成成分である脂肪酸の一種で、過剰摂取により、心筋梗塞などの冠動脈疾患が増加する可能性が高いとされています。常温では液体の植物油脂を固形の状態に製造・加工する段階や、植物油脂を製造過程で高温処理する際、油脂の構造が変わることにより生成されます。マーガリンはこの製法で液体から個体に変えてバターに似たように作られます。このようにトランス脂肪酸は加工食品に多く含まれています。
※不飽和脂肪酸は熱・光・空気などで酸化しやすく、酸化すると作用の低下により健康に悪影響をおよぼすこともあります。
※摂りたい油脂とはいえ、摂り過ぎはカロリーオーバーにつながるため注意が必要です。
脂質の適正量の範囲内で、できるだけ良質な油を摂りましょう。
特に、お菓子やアイスなどを購入する際は「原材料名」もチェックしてみましょう。「ショートニング」や「植物油脂」はトランス脂肪酸を多く含みます。植物油脂は体に良いと思われがちですが、製造・加工する段階で質が悪化するため、加工食品に含まれる場合には注意が必要です。
食物繊維を積極的に摂る
食物繊維は「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」に分かれ、それぞれ異なる作用があります。特に「水溶性食物繊維」は、腸の中でネバネバとしたゼリー状に変化し、そのネバネバがコレステロールや脂肪の吸収を促す胆汁酸や炭水化物などを吸着し、体外へ排出してくれます。
水溶性食物繊維を多く含む食品
- 麦類(大麦、オートミール、もち麦など)
- 海藻類(昆布、ワカメなど)
- 果物(りんご、いちご、みかんなど)
不溶性食物繊維を多く含む食品
- 野菜(ごぼう、レンコン、とうもろこしなど)
- 豆類(大豆、小豆、納豆など)
- きのこ類
両方含む食品
- ネバネバ食品(納豆、オクラ、長芋、なめこなど)
「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」は1:2のバランスで取り入れることが理想とされています。水溶性食物繊維は野菜からは摂取しにくいため、意識的に取り入れるようにしましょう。
手軽なのは、乾燥の海藻ミックスや糸寒天です。ひとつかみ程度の量を、お湯でふやかしてからサラダに加えたり、汁物に入れるだけでも効果的です。また、洋菓子を食べる習慣のある人は、洋菓子を果物に変えることで不足しがちな食物繊維を補い、質の悪い脂質を減らすことができます。
脂質に関しては「見えない油に注意しながら1日の摂取量を意識すること」「良質な油を摂ること」「食物繊維を摂って不要な脂質を体から出すこと」を心がけてみましょう。
脂質異常症に関する食事療法については以下の記事でもご紹介しています。
サルスクリニックにはいつも管理栄養士がいます
サルスクリニックには医師や看護師だけでなく、管理栄養士が常駐しています。
食生活だけでなく、ライフスタイルやご職業などの背景を踏まえ、実行できる食事療法を患者様と共に考え、その継続をサポートします。お気軽にご相談ください。
【参考文献】
- 女子栄養大学出版部「毎日の食事のカロリーガイド第3版」監修:香川明夫. 2018年12月25日 第3版発行
- 厚生労働省 公式HP 飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、トランス脂肪酸
- 農林水産省 公式HP すぐにわかるトランス脂肪酸