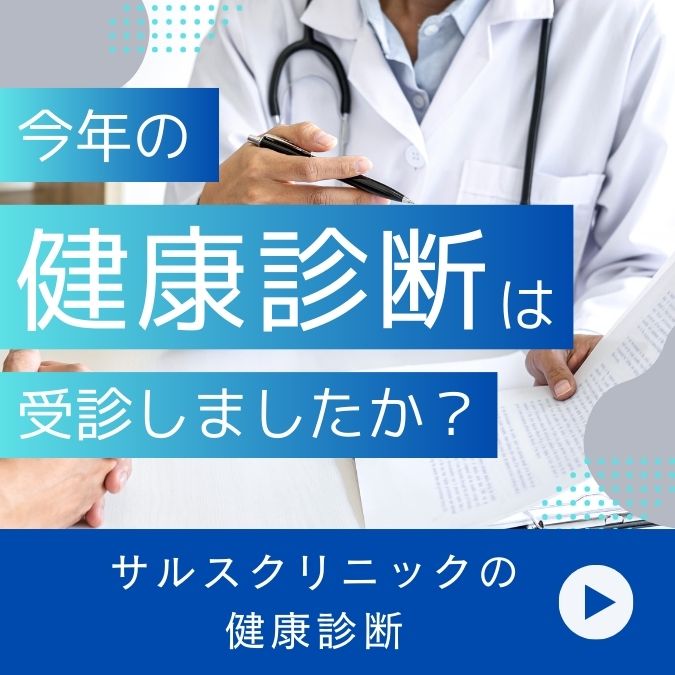食中毒とは
食中毒とは、有害な微生物(細菌・ウイルスなど)や、化学物質、自然毒、寄生虫などが付着または混入した食品や飲料を摂取することで引き起こされる、健康被害(主に下痢・嘔吐・腹痛・発熱など)の総称です。食中毒は原因により、以下のように分類されます。
主な食中毒の種類と原因
- 細菌性食中毒
感染型:サルモネラ、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌(O157など)、ウエルシュ菌など
毒素型:黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌など - ウイルス性食中毒
ノロウイルス、ロタウイルスなど - 自然毒食中毒
フグ毒、貝毒、毒キノコ、じゃがいもの芽に含まれるソラニンなど - 化学性食中毒
農薬、洗剤、重金属などの化学物質によるもの(水銀、ヒ素、ヒスタミンなど) - 寄生虫食中毒
アニサキスなど - その他
原因不明なもの
厚生労働省の統計(食中毒発生状況)によると、直近5年間の食中毒発生件数は700~1200件の間で推移しており、令和6年には1,037件(患者数:14,229人)と報告されています。食中毒は夏に多いイメージがありますが、実際には一年を通して発生しており、特に6月から9月の暑い時期は気温と湿度が高く細菌が繁殖しやすいため、細菌性の食中毒が多く見られます。
一方で、ウイルスは低温でも生存できるため、冬(12月〜3月)は、感染力の強いノロウイルスなどによるウイルス性食中毒が流行しやすいです。また、春や秋には、毒キノコやフグなどの自然毒による食中毒が、他の季節と比べて多く発生する傾向があります。
なぜ夏場に細菌性食中毒が増えるの?
前述のとおり、梅雨や夏の時期は、気温と湿度が高くなるため、細菌が増殖しやすい環境が整います。このため、細菌性の食中毒の発生件数が増加する傾向があります。一般的に、多くの食中毒菌は約20℃で増殖を始め、25〜37℃の中温域で最も活発に増殖します。特に、人の体温に近い温度で増殖のスピードが最も速くなります。
また、細菌の多くは湿度の高い環境を好むため、梅雨のようにジメジメした時期から食中毒のリスクが高まります。
家庭でできる!食中毒予防11のポイント
1.手洗いの徹底
手洗いは、食中毒予防の基本中の基本です。なぜなら、人の手が、食中毒を引き起こす病原微生物の「運び屋」になる可能性があるからです。
日常生活の中であらゆる場所やものに触れる手には、目に見えない病原微生物が付着し、手洗いをせずに調理をおこなうことで食品に移り、食中毒を引き起こす原因となるのです。しかし、これらの病原微生物は、正しい方法で手を洗うことでしっかりと洗い流すことができます。調理や食事の前には、「こまめに」「丁寧に」手洗いをする習慣をつけましょう。
【正しい手洗いの手順とポイント】
- 流水で手を十分に濡らす
手全体をしっかり濡らすことで、石けんが泡立ちやすくなります。 - 石けんをつけて手のひらを洗う
十分に泡立てて、汚れやウイルスを浮かせるイメージで洗いましょう。 - 手の甲を洗う
手のひらだけでなく、手の甲も汚れや菌が付きやすいため、忘れずに洗いましょう。 - 指の間を洗う
指と指の間は汚れが残りやすい場所です。しっかりと洗いましょう。 - 指先・爪の間を洗う
爪の間は菌がたまりやすい場所です。手のひらに爪を立てるようにして洗うと効果的です。 - 親指を洗う
親指は見落としがちな部分です。反対の手でしっかり握って、ねじるように洗いましょう。 - 手首を洗う
手首までしっかり洗うことで、腕側からの汚れも防止できます。 - 流水でよく洗い流す
石けんと一緒に浮き上がった汚れや菌を、念入りに洗い流しましょう。 - 清潔なタオルやペーパータオルで拭き、乾かす
湿った手は菌が付着しやすくなるため、しっかりと乾かすことが大切です。
2.食品の購入時の注意点
肉・魚・野菜などの生鮮食品は、できるだけ新鮮なものを選びましょう。表示のある食品については、消費期限や保存方法などをよく確認してから購入することが大切です。
購入した食品は、肉汁や魚の水分が他の食品に付かないよう、種類ごとにビニール袋などで分けて包みましょう。特に冷蔵・冷凍が必要な食品は、買い物の最後に選び、購入後はなるべく早く持ち帰るように心がけましょう。
3.食材は適切に保存(冷蔵・冷凍)
買い物を終えたら、食品はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。時間が経過すると細菌が増殖する恐れがあるため、冷蔵・冷凍食品は温度管理が非常に重要です。食中毒菌の増殖を防ぐためには、冷蔵は10℃以下、冷凍は−15℃以下で保存しましょう。多くの細菌は5℃以下で増殖がほとんど停止しますが、10℃を超えると活発に増殖し始めます。
また、−15℃以下で細菌の活動は完全に止まりますが、死滅するわけではありません。そのため、解凍後はなるべく早く調理し、中心までしっかり加熱して食べることが大切です。肉や魚などの生鮮食品は、ビニール袋や密閉容器に入れて保存し、ドリップなどが他の食品に付着しないよう注意しましょう。
4.台所の衛生チェック
調理を始める前に、キッチン全体を見渡して、以下のポイントを確認しましょう。
- ゴミはきちんと捨てられているか
- タオルやふきんは清潔なものか
- 石けんはすぐに使えるか
- 調理台の上は整理され、広く使える状態か
これらのポイントを確認し、衛生的な環境を整えることが、食中毒を防ぐ第一歩になります。
5.生肉や生魚の取り扱いに注意!
生肉や生魚のドリップが、果物やサラダなどの生で食べる食品や調理済みの食品に付かないように注意しましょう。
生肉や生魚を切った後の包丁やまな板は、洗剤でよく洗ったあと、熱湯をかけて消毒しましょう。可能であれば、用途別に包丁やまな板を使い分けるとより安全です。(肉用、魚用、野菜用など)
6.野菜もしっかり洗う
ラップで包装されている野菜やカット野菜も、調理や食事の前に必ずよく洗いましょう。見た目が清潔でも、加工や包装の過程で菌や汚れが付着していることがあります。
7.冷凍食品の解凍方法に注意!
調理台に置いたままの「室温解凍」はNG!常温では食中毒菌が増殖する危険性があります。
【安全な解凍方法】
- 冷蔵庫で自然解凍する
- 電子レンジの解凍機能を使用する
- 気密容器に入れ、流水で解凍する(食品が水に直接触れないように注意しましょう)
【解凍後の注意点】
再冷凍・再解凍の繰り返しは避けましょう。食材の品質が低下するだけでなく、細菌が増殖しやすくなります。
8.調理器具の洗浄と消毒
生肉や生魚に付着した菌が、他の食材に移る「二次汚染」を防ぐため、調理器具は、使用後すぐに洗剤と流水でしっかり洗いましょう。ふきんが汚れていると感じたら、清潔なものに交換することも大切です。
包丁・まな板・食器などは、洗剤で洗ったあとに熱湯をかけて消毒しましょう。ふきん・たわし・スポンジなどは、次亜塩素酸ナトリウム製剤(台所用漂白剤)に一晩つける、または煮沸消毒が効果的です。調理器具の衛生管理は、食中毒予防の基本です。使用後はすぐに洗い、消毒する習慣を身につけましょう。
9.加熱調理はしっかりと!
加熱して食べる食品は、中心までしっかり火を通すことが大切です。十分に加熱することで、たとえ食中毒菌が付着していても殺菌できます。食品の中心温度が75℃以上で1分以上(ノロウイルスは85℃〜90℃で90秒以上)を目安に加熱することが推奨されています。調理の途中で中断する場合は、食品を常温で放置せず、冷蔵庫に入れて保存しましょう。再び調理する際は、再加熱をしっかり行うことが大切です。
電子レンジを使用する場合は、電子レンジ対応の容器とふたを使用しましょう。食材によっては加熱ムラが出やすいため、時々かき混ぜ、指定された調理時間を守って加熱不足にならないよう注意しましょう。
10.調理後の食品はすぐに冷蔵し、常温放置を避ける
調理済みの食品でも、常温で2時間以上放置すると、食中毒菌が増殖するおそれがあります。特に夏場など、気温が高い時期は要注意です。お弁当などを持ち運ぶときは、保冷剤や保冷バッグなどを活用して、できるだけ低温を保つ工夫をしましょう。
11.作り置きや残りものの管理に注意
一度調理した食品でも、保存方法が不適切だと細菌が繁殖するおそれがあります。作り置きは小分けにして、できるだけ早く冷まし(急冷)、冷めたらすぐに冷蔵保存しましょう。食べるときは、中心部までしっかり火を通して加熱することが大切です。
食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない」「増やさない」「やっつける」です。本コラムでご紹介した対策を日々の生活に取り入れることで、食中毒を効果的に防ぐことができます。
とは言え、完全に防げるわけではありません。もし、腹痛、下痢、嘔吐などの症状が見られた場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診しましょう。
サルスクリニックにはいつも管理栄養士がいます
サルスクリニックには、医師や看護師だけでなく、管理栄養士が常駐しています。食事や栄養についてお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。みなさまが健康で充実した生活を送れるようにサポートいたします。
【参考文献】
- 一般財団法人 食品産業センター.「HACCP関連用語集|HACCP関連情報データベース」
- 千葉県.「食中毒の分類・予防」.2024年9月18日
- 東京都保健医療局.「知って安心トピックス|食品衛生の窓」
- 厚生労働省.「4.食中毒統計資料」
- 厚生労働省.「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」
- 政府広報オンライン.「食中毒予防の原則と6つのポイント」.2024年10月21日
- 公益社団法人日本食品衛生協会.「食中毒予防に関する意見交換会 ~食中毒予防のポイントを学ぼう~ 食中毒予防のための衛生的な手洗いについて」.平成27年6月26日(東京)、7月14日(岡山)開催
- 公益社団法人 日本食品衛生協会.「手洗いマニュアル」
- 厚生労働省.「ノロウイルスに関するQ&A」.2021年11月19日