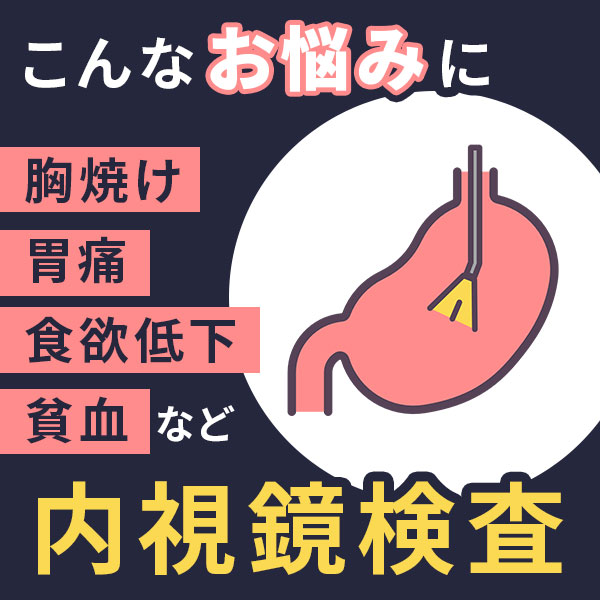身体状況の結果 ~20代女性のやせについて~
令和元年以降、成人の肥満者は男女ともに大きな増減がみられないのに対し、若年女性においては、BMI18.5kg/m²未満の「低体重(やせ)」の割合が20.2%と、平成23年以降最も高い結果となりました。健康問題や次世代への影響も懸念されるため、若年女性の「やせ」問題は社会的に無視できない課題となっています。
日本における若い女性の「やせ」は、先進国の中でも特に高い割合を占めていると言われています。
(参考:https://www.hcc.keio.ac.jp/ja/research/assets/files/41-9.pdf)
その理由として、SNSなどのメディアを通じて「やせていることは美しいこと」という価値観が浸透し、やせ願望を持つ女性が少なくないことが背景にあります。過度なダイエットや食事制限により、免疫力の低下や月経不順、骨密度の減少など、健康に多くの悪影響を及ぼす恐れがあります。
2025年4月、日本肥満学会は女性の低体重や低栄養が招く健康障害を、新たな疾患として位置付ける方針を発表しました。「女性の低体重・低栄養症候群(FUS)」として新たな疾患の名称を定め、日本産科婦人科学会などの5学会と連携して、診断基準などを決定しました。18歳から閉経前までの女性を対象に、食事や運動による治療や予防法の確立を目指しています。
女性の健康を守るためにも、適切な栄養摂取とバランスの取れた食生活の重要性が再認識されるべきといえるでしょう。
栄養・食生活に関する状況 ~野菜の摂取不足について~
栄養摂取状況の分析では、野菜の摂取不足の実態が明らかになりました。20歳以上の野菜摂取量の平均値は256.0gで、厚生労働省が推奨する目標値(350g以上/日)に達していないことが分かりました。この野菜摂取量の傾向は、過去10年間で男性では有意に減少し、女性でも平成27年以降、有意に減少しています。さらに、野菜摂取量は男女ともに20代が最も少なく、高齢になるほど増加する傾向にあります。
なお、当院で栄養指導を受けている方の多くは積極的に野菜を摂るよう心がけていらっしゃいますが、1日350gという目標量を達成するのは、やはり簡単なことではありません。
野菜にはビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、免疫力の向上や生活習慣病の予防に重要です。そのため、若年層のうちから、これまで以上に意識的に野菜を摂取する習慣の定着が求められます。
身体活動・運動に関する状況 ~運動習慣の低下について~
調査によると、運動習慣のある人の割合は男性で36.2%、女性で28.6%であり、特に女性の20代では14.5%と低い水準でした。また、成人の1日の平均歩数は男性で6,628歩、女性で5,659歩と、いずれもこの10年間で減少傾向にあります。これは、コロナ禍以降のテレワークの普及や生活スタイルの変化が影響していると考えられます。運動不足は生活習慣病のリスクを高めるため、日常生活における運動習慣の促進が必要です。
また、当院に通院される方の中にも、コロナ禍で運動量が減ったことにより、体重の増加や血液データの悪化が見られる方が多くいらっしゃいます。
厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」では、成人は「1日60分以上の身体活動」「1日8,000歩以上」の身体活動を行うことが推奨されていますが、実際には多くの人がこれに達していない状況ということが浮き彫りになりました。日常生活での活動量を増やす工夫が求められます。
地域のつながりに関する状況 ~社会的孤立について~
調査では、居住する地域の人々が「お互いに助け合っている」と思う者の割合は41.5%であり、平成23年以降の調査で有意に減少しています。さらに、「地域の人々とのつながりは強い」と思う者の割合は31.6%で、どちらの項目も年齢階級が上がるにつれ、その割合は高くなっていることから若年層の社会的孤立が見られます。
孤食や地域との関わりの希薄さは、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性もあるため、地域におけるコミュニケーションの重要性が増しています。住民同士がつながることで、情報共有や助け合いが生まれ、健康に対する意識の向上にもつながります。
健康づくりは個人の努力だけでなく、人とのつながりや地域全体の協力によって成り立つものであり、地域とコミュニケーションの力がその鍵を握っているといえるでしょう。
最後に
以上の考察を踏まえ、今後の健康政策では、若年層を対象とした健康への意識作りの強化や、運動習慣の促進、栄養バランスの取れた食生活の普及が必要であるということがわかりました。
なお、「国民健康・栄養調査」については毎年実施されており、結果が公開されます。
私達日本人の生活習慣や健康の現状を知り、これからの指標になる重要な調査のため、興味がある方はこちらから過去データを閲覧するのもおすすめです。
(「国民健康・栄養調査」、厚生労働省)
サルスクリニックにはいつも管理栄養士がいます
当院の栄養指導では、日々のお食事に関するアドバイスはもちろん、生活習慣の一環としての運動についてもご相談いただけます。ひとりひとりのライフスタイルに寄り添いながら、無理のない健康づくりをサポートいたします。お気軽にご相談ください。
【参考文献】