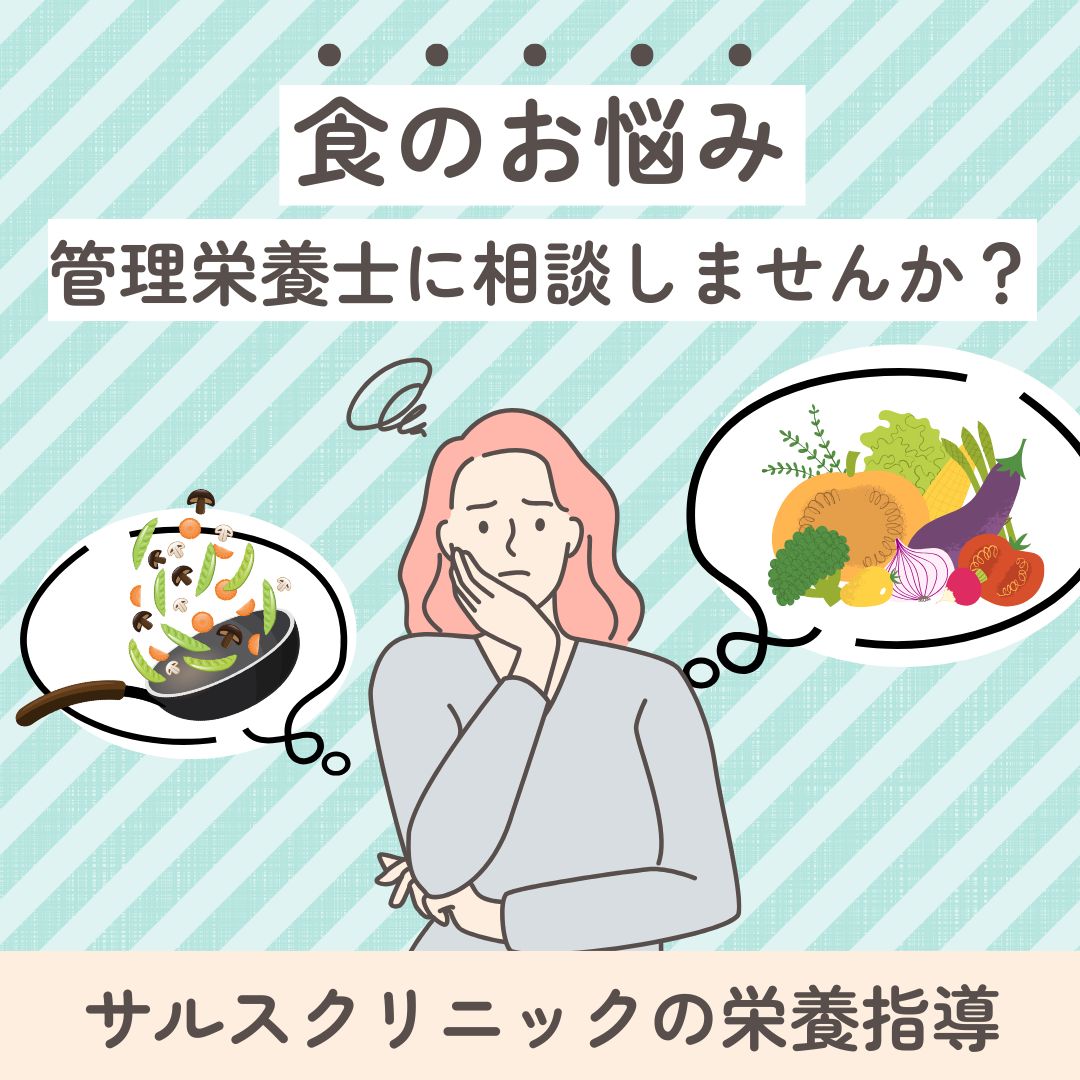炭水化物とは?
糖質と食物繊維を合わせたものを総称して炭水化物と呼びます。糖質は、体内で吸収されてエネルギー源になりますが、食物繊維はほとんどが消化吸収されないため、エネルギー源にはなりません。
エネルギー源になる糖質は、単糖類(ぶどう糖や果糖など)・二糖類(しょ糖や乳糖など)・多糖類(デンプンなど)に細かく分類され、これらを「利用可能炭水化物」と呼びます。利用可能炭水化物とは、エネルギーとして利用できる炭水化物のことを指します。一方で、糖アルコールや食物繊維は難消化性で利用効率が悪いため、「利用不能炭水化物」と呼ばれています。
炭水化物はどんな食品に含まれているの?
炭水化物は主に、ご飯・パン・麺類などの主食に該当する食品や、芋類、果物、清涼飲料水などのジュースやお菓子などに多く含まれています。それぞれの食品ごとに、含まれている炭水化物(糖質)の種類や量に差があるため、注意が必要です。
例えば、主食に多く含まれているのは多糖類であるデンプンです。果物には果糖、清涼飲料水やお菓子などにはぶどう糖として多く含まれています。
炭水化物(糖質)の役割は?
体のエネルギー源となる炭水化物(糖質)は、食物として摂取された後、唾液中のアミラーゼという消化酵素により分解され、胃→十二指腸→小腸へ送られていく過程で、単糖であるぶどう糖まで分解されて吸収されます。血液中のぶどう糖はグルコースと呼ばれ、各細胞に運ばれて、エネルギー源として利用されます。たんぱく質や脂質からもエネルギーを作ることはできますが、最も効率よくエネルギーを作れる栄養素が炭水化物(糖質)なのです。
また、エネルギーを作るときには、ビタミンB1が必要です。ビタミンB1が不足した状態だと、スムーズにエネルギーを作ることができず、余分な糖質が体内に溜め込まれてしまい肥満の原因となります。
ビタミンB1は、豚肉や赤身肉、大豆や種実類、玄米など雑穀類などに多く含まれています。エネルギーを効率よく作るためにも、栄養バランスの整った食事を心がけましょう。
炭水化物(糖質)の過剰摂取や不足による影響は?
炭水化物(糖質)を摂りすぎると、肥満の原因になったり、生活習慣病になる危険性が高まります。炭水化物(糖質)を過剰に摂取することで、余分なぶどう糖が脂肪細胞に運ばれて体脂肪として蓄積し、肥満の原因になります。また、血糖値が急激に上昇することで糖尿病などのリスクも高まります。さらに、果物に多く含まれている果糖は、摂りすぎると肝臓で中性脂肪に合成されて高トリグリセライド血症の原因になります。砂糖などのショ糖は虫歯の原因になることもあります。
逆に、炭水化物の不足が続くと、疲れやすさを感じたり、脳のエネルギー源が不足するためぼーっとしてしまうことがあります。炭水化物(糖質)が不足し続けると、体内にあるたんぱく質や脂質を使用してエネルギーを作り出すようになるため、本来であれば筋肉や血液など、身体を作るために使用したいたんぱく質が、エネルギーの生成に使用されてしまい、筋肉量の低下を招くことで体の不調につながります。
健康的な成人のご飯の適量は、両手に収まるサイズのお茶碗1杯分が、1食あたりの目安です。炭水化物(糖質)は、多すぎず少なすぎず、適量で食べることを心がけましょう。
サルスクリニックにはいつも管理栄養士がいます
サルスクリニックには医師や看護師だけでなく、管理栄養士が常駐しています。食生活だけでなく、ライフスタイルやご職業などの背景を踏まえ、実行できる食事療法を患者様と共に考え、その継続をサポートします。お気軽にご相談ください。
【参考文献】
- 改定第7版 病態栄養専門管理栄養士のための病態栄養ガイドブック 編集:日本病態栄養学会 南江堂
- 日本人の食事摂取基準2020年版 監修:伊藤貞嘉、佐々木敏 第一出版